
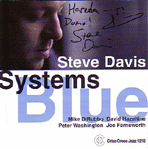

「ヴォイスの客」はらすすのジャズよもやま話
連載第12回 「ミスターケリーズ」がN.Y.と化した夜
2002年10月13日日曜日の夜、僕は大阪梅田の「ミスターケリーズ」へEric Alexander Quintetの演奏を聴きに出かけました。Eric Alexanderと言えば、本コラムの第2回および第9回でも彼について紹介していますが、現在僕の最もお気に入りのテナーサックス奏者と言うべき人なのです。
当日のメンバーは、Steve Davis(tb)、Harold Mabern(p)、Nat Reeves(b)、Joe Farnnsworth(ds)といった面々であり、どうもEric Alexanderは一定の気心の知れたメンバーのみと一緒に演奏する事を好む傾向があるようです。と言うのも、サイドメンのうちでHarold Mabern以下のリズムセクションは前回1999年にQuartetで来日して原宿「Keynote」でライブレコーディングを残した際のメンバーと全く同一ですし、トロンボーンのSteve DavisおよびドラムスのJoe Farnnsworthは本コラムの第2回で紹介した“One for All”というオールスターグループのメンバーであり、従って当日のサイドメンはEric Alexanderのレギュラーカルテットと“One for All”のメンバーとが合体したような構成から成っていました。
それだけに、各メンバー達との呼吸もピッタリで、また各曲で随所に細かい仕掛けがふんだんにみられ、最初の一音の出だしからアンコールまでの1時間余り、息つく暇もないような感動に次ぐ感動のライブとなりました。その結果、当日決して広くはない「ミスターケリーズ」の店内は当然ながら立錐の余地もない程超満員の客で埋め尽くされていたのですが、観客達のノリも最高潮で、店内は興奮のるつぼと化しました。僕も今までに素晴らしいジャズの演奏は随分聴いてきたつもりだったのですが、この日の演奏はN.Y.の若手トップグループによるまさしく“現在進行形”のモダンジャズであり、かつて味わった事のないような身の毛もよだつような感動の嵐を体験する事ができました。そして、次第に“ここは本当に大阪なんやろか?”と今自分のいる場所が信じられず、まるで彼等の本拠地であるN.Y.のジャズクラブである「Smoke」(実際にはこんな場所には一度も行った事はないのですが…)にでも身を置いているような錯覚すら感じるといった状態でした。
それにしてもつくづく感じるのは、アメリカ人ジャズメン達の底力のすごさです。ちょうどこの日の朝、僕はテレビでメジャーリーグのワールドシリーズ戦を観戦しており、その際にキヤッチャーがほとんど坐ったままの姿勢でセカンドへ送球して盗塁を試みたランナーをアウトにしたり、サードからファーストへ矢のような送球を送るといったシーンを目の当たりにして、“こんなものすごいシーンは日本のプロ野球では決してお目にかかれないなあ”と溜め息をついていたのですが、まさしくその日の夜に全く同じ気分をまたもや味わうハメとなってしまいました。
演奏終了後には、「ミスターケリーズ」の店の前に多くのファンが集まり、にわかサイン会および写真撮影会状態となりました。僕も、Eric Alexander・Steve Davis・Joe Farnnsworthにはそれぞれ持参していた彼等のリーダーアルバム「Live at Keynote」(ビデオアーツ)、「Dig Deep」(Criss Cross)、「Beautiful Friendship」(Criss Cross)にサインを頂きました。この3人はいずれも30歳代前半の白人で、まるでアメリカの学園ドラマに出てくるような若者がそのまま大きくなったようなチャーミングな雰囲気を漂わせた人達でした。一方、ピアノのHarold Mabernは現在66歳の海坊主のようないかつい風貌の黒人で(でも笑うと可愛い)、他のメンバー達から見るとちょうど父親のような世代に属し、実際にEric Alexanderからは日本語で“私の先生”“私の師匠”等と紹介されており、メンバー達の彼に対する畏敬の念が深く感じ取れました。
Ericに「次回は是非とも“One for All”のメンバーで日本に来て下さい」と話しかけると、「“One for All”のメンバー達も是非日本に行きたいと切望しているんだよ」との返事であり、ますます楽しみはつのるばかりです。このような魅力的なライブを体験すると、その後何日間もずっと熱にうなされたような感激が体内に貯留し、毎日ハッピーな気分で過ごす事が出来るのです。
ではまた来月、どうぞ皆様も素晴らしいジャズライブに足を運んでみて下さい。
(2002年11月10日 記)
連載第12回 「ミスターケリーズ」がN.Y.と化した夜
2002年10月13日日曜日の夜、僕は大阪梅田の「ミスターケリーズ」へEric Alexander Quintetの演奏を聴きに出かけました。Eric Alexanderと言えば、本コラムの第2回および第9回でも彼について紹介していますが、現在僕の最もお気に入りのテナーサックス奏者と言うべき人なのです。
当日のメンバーは、Steve Davis(tb)、Harold Mabern(p)、Nat Reeves(b)、Joe Farnnsworth(ds)といった面々であり、どうもEric Alexanderは一定の気心の知れたメンバーのみと一緒に演奏する事を好む傾向があるようです。と言うのも、サイドメンのうちでHarold Mabern以下のリズムセクションは前回1999年にQuartetで来日して原宿「Keynote」でライブレコーディングを残した際のメンバーと全く同一ですし、トロンボーンのSteve DavisおよびドラムスのJoe Farnnsworthは本コラムの第2回で紹介した“One for All”というオールスターグループのメンバーであり、従って当日のサイドメンはEric Alexanderのレギュラーカルテットと“One for All”のメンバーとが合体したような構成から成っていました。
それだけに、各メンバー達との呼吸もピッタリで、また各曲で随所に細かい仕掛けがふんだんにみられ、最初の一音の出だしからアンコールまでの1時間余り、息つく暇もないような感動に次ぐ感動のライブとなりました。その結果、当日決して広くはない「ミスターケリーズ」の店内は当然ながら立錐の余地もない程超満員の客で埋め尽くされていたのですが、観客達のノリも最高潮で、店内は興奮のるつぼと化しました。僕も今までに素晴らしいジャズの演奏は随分聴いてきたつもりだったのですが、この日の演奏はN.Y.の若手トップグループによるまさしく“現在進行形”のモダンジャズであり、かつて味わった事のないような身の毛もよだつような感動の嵐を体験する事ができました。そして、次第に“ここは本当に大阪なんやろか?”と今自分のいる場所が信じられず、まるで彼等の本拠地であるN.Y.のジャズクラブである「Smoke」(実際にはこんな場所には一度も行った事はないのですが…)にでも身を置いているような錯覚すら感じるといった状態でした。
それにしてもつくづく感じるのは、アメリカ人ジャズメン達の底力のすごさです。ちょうどこの日の朝、僕はテレビでメジャーリーグのワールドシリーズ戦を観戦しており、その際にキヤッチャーがほとんど坐ったままの姿勢でセカンドへ送球して盗塁を試みたランナーをアウトにしたり、サードからファーストへ矢のような送球を送るといったシーンを目の当たりにして、“こんなものすごいシーンは日本のプロ野球では決してお目にかかれないなあ”と溜め息をついていたのですが、まさしくその日の夜に全く同じ気分をまたもや味わうハメとなってしまいました。
演奏終了後には、「ミスターケリーズ」の店の前に多くのファンが集まり、にわかサイン会および写真撮影会状態となりました。僕も、Eric Alexander・Steve Davis・Joe Farnnsworthにはそれぞれ持参していた彼等のリーダーアルバム「Live at Keynote」(ビデオアーツ)、「Dig Deep」(Criss Cross)、「Beautiful Friendship」(Criss Cross)にサインを頂きました。この3人はいずれも30歳代前半の白人で、まるでアメリカの学園ドラマに出てくるような若者がそのまま大きくなったようなチャーミングな雰囲気を漂わせた人達でした。一方、ピアノのHarold Mabernは現在66歳の海坊主のようないかつい風貌の黒人で(でも笑うと可愛い)、他のメンバー達から見るとちょうど父親のような世代に属し、実際にEric Alexanderからは日本語で“私の先生”“私の師匠”等と紹介されており、メンバー達の彼に対する畏敬の念が深く感じ取れました。
Ericに「次回は是非とも“One for All”のメンバーで日本に来て下さい」と話しかけると、「“One for All”のメンバー達も是非日本に行きたいと切望しているんだよ」との返事であり、ますます楽しみはつのるばかりです。このような魅力的なライブを体験すると、その後何日間もずっと熱にうなされたような感激が体内に貯留し、毎日ハッピーな気分で過ごす事が出来るのです。
ではまた来月、どうぞ皆様も素晴らしいジャズライブに足を運んでみて下さい。
(2002年11月10日 記)